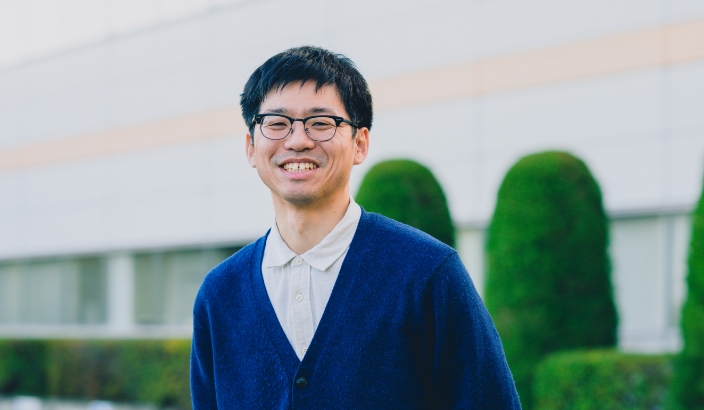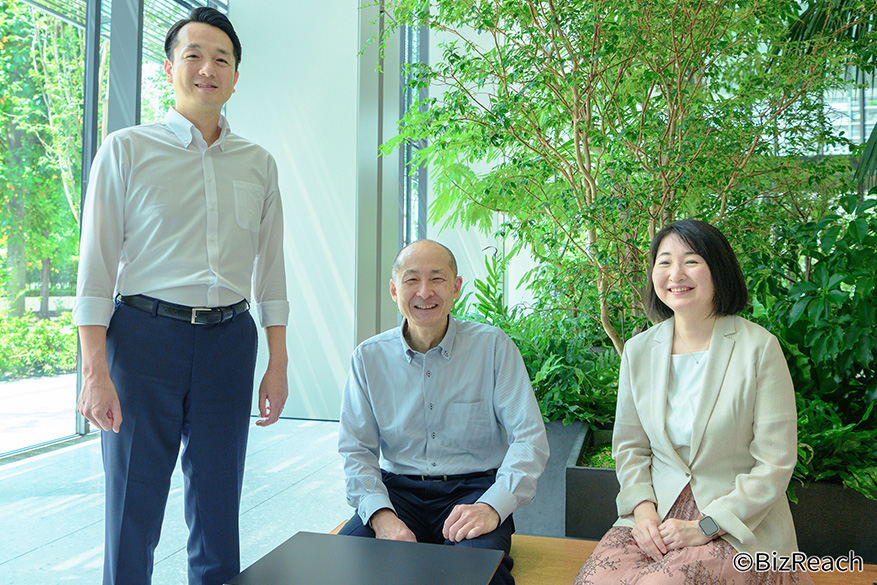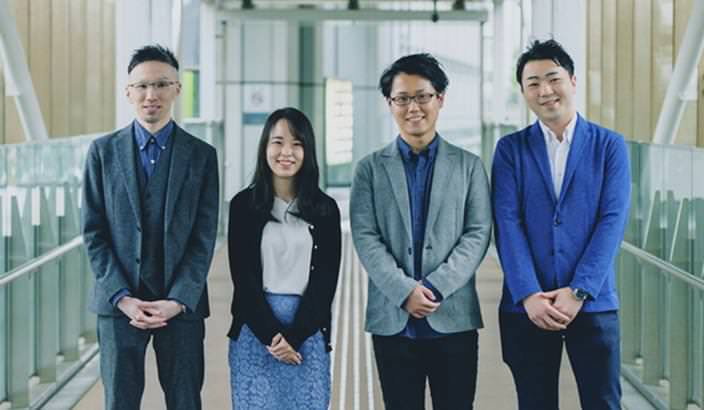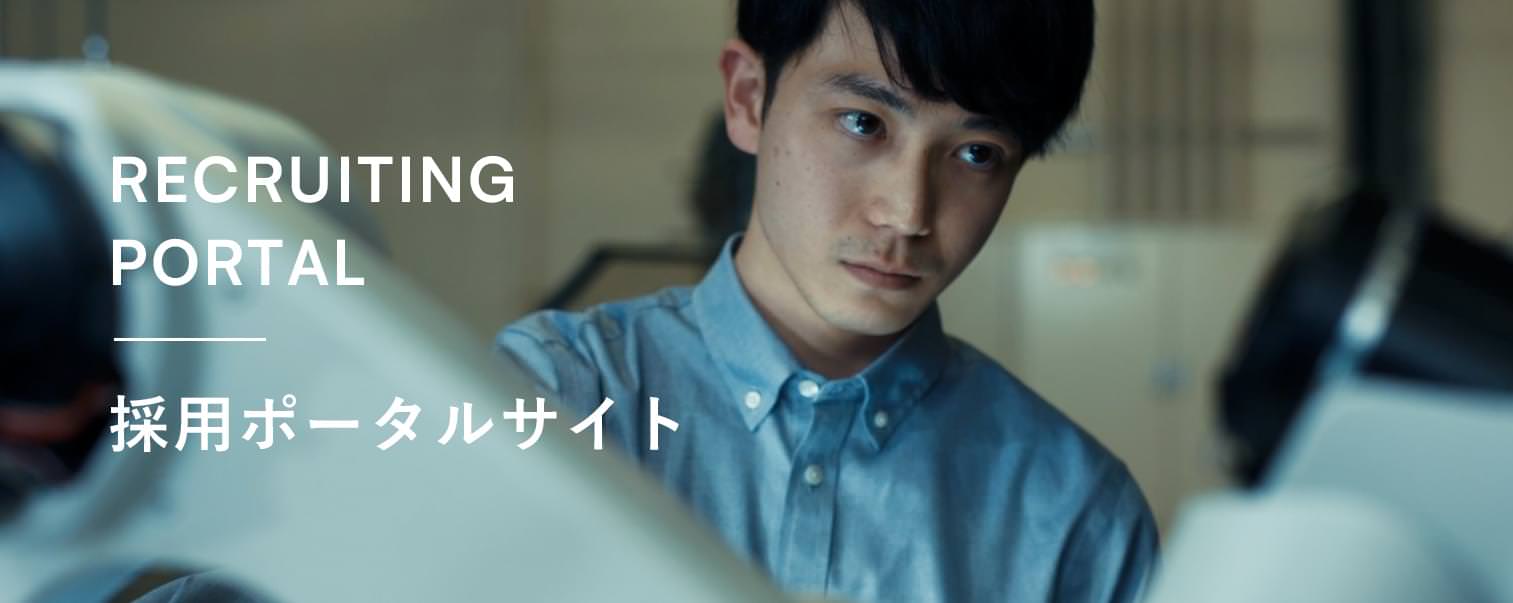Interview
技術で人の可能性を広げる、
新しいロボティクスの現場
次世代事業の創出に向けて、事業の新たな柱であるビジョンロボティクス本部を2025年4月に立ち上げた株式会社ニコン。2030年に「人と機械が共創する社会の中心企業」になるというありたい姿を掲げ、100年以上の歴史の中で培った光利用技術や精密技術を武器に、技術革新を行っています。同社の技術開発の魅力や展望について、ビジョンロボティクス本部長の一ノ瀬剛氏にお話を伺いました。
出典:ビズリーチ掲載記事(2025年6月26日公開)より転載
ロボティクス事業で市場を切り開き、
人と機械の未来を創る
ビジョンロボティクス本部長/一ノ瀬 剛

2025年4月より、新規事業のビジョンロボティクス本部が発足した背景を教えてください。
「ビジョンロボティクス本部」は、ニコンの次なる100年を見据えた新事業の柱として、ロボティクス分野に本格的に取り組むために発足しました。背景には、2030年に向けたありたい姿である「人と機械が共創する社会の中心企業となる」という目標の存在があります。 その実現に向けて、当社ではこれまで「次世代事業創出」という課題のもと、複数のプロジェクトを立ち上げ、開発段階からお客様と対話を重ねてきました。その中で、特に強く感じたのが、高精度な作業を誰もが簡単に行える「ものづくりの自動化」への期待です。そうしたニーズに対し、当社が培ってきた「光利用技術」や「精密技術」といった強みを応用することで、解決策を提示できるのではないかと考えました。検討を重ねた結果、機械に人間らしさを与える「ビジョンロボティクス」という分野に技術を生かすことで、より実効性のあるソリューションが提供できると確信し、本部の設立に至りました。
ビジョンロボティクス本部の事業内容と、開発されている製品・サービスについて教えてください。
ビジョンロボティクス本部は、研究開発と事業化の両方を担う、ハイブリッド型の組織です。当社の場合、製品の販売や収益化を担う部門と、研究開発や新規事業創出を担うという、役割や機能に応じた組織体となっていますが、私たちはその両方を自ら推進しています。アイデアの創出から製品販売、サービスサポートに至るまでを一貫して手がけるのは、当社の中でも極めて珍しい体制です。 これまでに開発した製品として、2024年10月に販売を開始した「ロボットビジョンシステム」があります。これは私たちが基礎開発レベルから始めて、製品販売まで行った実例の1つです。ニコンが培ってきた光利用技術と画像処理技術をベースに、最大250fpsの高速画像処理、複雑なワークの認識精度、設置や運用のしやすさを実現しました。このようにプロジェクトをアイデアの段階から育て、お客様のお手元までお届けして事業として成り立っているのが、当本部の最大の特徴です。 現在も、動体追尾を可能にした「トラッキングカメラ」や、高速・高精度に空間座標を測定できるレーザー測定システムの「ローカライザー」のほか、さまざまなツールを取り付けられる「自律動作型ロボット」など、複数の新プロジェクトが同時進行しています。
部門を越えた開発体制と多様な人材が生む、
新時代のものづくり
本部は第一開発部と第二開発部に分かれていますが、開発体制や業務の進め方に違いはありますか。
開発体制としては、第一開発部が機械設計・システム設計を、第二開発部がソフトウエアや電気系ハードウエア、アルゴリズム開発を担当しており、それぞれの専門技術分野によって役割が分かれています。一方で、業務の進め方に関しては、両部ともに共通のスタイルを採用しています。 私たちの開発スタイルの特徴は、従来のウォーターフォール型とは異なり、アイデアの初期段階から各分野のメンバーが横断的に関与して意見を出し合う点です。プロジェクトの着想段階から各分野のプロフェッショナルに加わってもらうことで、企画の初期段階からでも実現可能性の高いアイデアに早期にブラッシュアップすることができます。結果として、技術課題の早期抽出や、短いスパンでの製品化が可能です。 当部門には、ニコンが伝統的に培ってきた技術を推進できるメンバーに加え、外部でさまざまな経験を積み、仲間として合流してくれた異分野の知見を持つメンバーも多数在籍しています。そのため、開発現場は多様な視点からの意見が交わされ、互いに気付きや刺激を与え合える、発展的な環境です。
ビジョンロボティクス本部として、今後はどんな未来を見据えていますか。
これからのものづくりは、いわゆる「フィジカル空間(現実世界)」と「サイバー空間(仮想空間)」を密接に連携させて進めていく時代になっていくと考えています。これまでの製造業は、熟練の職人が現場で調整や組み立てを行うことが当たり前でしたが、今後は誰もが仮想空間上で事前にシミュレーションを行い、現実に反映するスタイルが主流になっていくはずです。 そこで鍵となるのが、現実空間の状況をリアルタイムに把握する計測技術とセンシング技術です。ニコンはこの分野に重要な、光利用技術と製造のアセットを多く持っています。そこに制御するための仕組みを組み合わせることで、これまでにない新しい価値を創出できると確信しています。 私たちは、現実と仮想が一体化した、効率的かつものづくりの自由度が増した未来を目指しています。その実現に向けて、ビジョンロボティクス本部は今後も技術とシステムの融合に挑み続けていきます。

新たな価値を生み出す現場で、
未来につながる力を磨く
ビジョンロボティクス本部の組織風土やチームの雰囲気について教えてください。
ビジョンロボティクス本部には、さまざまな価値観や専門性を持つ人材が集まり、互いに学び合いながら共創を進める、発展的で風通しの良い職場環境があります。メンバー同士の議論も非常に活発です。各分野の担当やマネジメントが垣根なく打ち合わせに参加し、同じ「ものづくりチームの一員」としてフラットに会話をしています。 実は、ロボット技術を活用した事業化にニコンとして本格的に取り組むのは、この本部が初めてです。立ち上げ当初は、社内にロボットに精通した人材がほとんどおらず、2~3人の体制でスタートしました。そこから現在の体制に至るまでに、ロボット開発に精通したエンジニアや、フィールドサポートができるエンジニアたちが私たちのビジョンに共感し、次々と加わってくれました。
ビジョンロボティクス本部で得られる経験や、成長機会はどのようなものがありますか。
当部門は、自分の専門分野だけに専念する環境ではありません。もちろん、個人の適性や希望に応じて専門知識の研鑽に集中し、スキルアップを図ることも十分可能です。一方で、例えば電気設計のエンジニアが機械設計やソフトウエアのメンバーと密に意見を交わしながら、新しい技術や製品の創出に取り組むこともできます。また、製品のマーケティングや事業戦略の検討に関わる機会もあり、多方面に携わる経験が得られます。 このように多様な分野に横断して関わることで、単一の専門スキルにとどまらず、複数の領域にまたがるマルチスキルを身につけることが可能です。こうした環境は非常に恵まれており、幅広い知識や視野を持つ人材に成長できると考えています。
ビジョンロボティクス本部で働くうえで、求められる資質やマインドセットについてお聞かせください。
まず挙げられるのは、空想や妄想が好きな方ですね。新しい価値を生み出すには、「こんなことができたら面白い」「これがあれば世の中が便利になるかもしれない」といった想像から始まることが多いためです。柔軟な発想力を持ち、日頃からアンテナを張っている方は、この仕事に向いていると思います。 また、他者を尊重しながらチームで協力して業務を進められる協調性も重要です。ニコンの技術アセットは大きな強みですが、それを生かすのはあくまで人と人との連携だからです。私たち開発部門の仕事は一人では完結しません。社内の他部署はもちろん、外部のパートナーやお客様とも密にコミュニケーションを取る必要があります。だからこそ、自分の力を生かしつつ周囲と調和して進められる人が、のびのびと活躍している印象です。
挑戦を通してキャリアを
柔軟に築けるニコンの現場
幅広いポジションで採用強化されていると伺っています。入社される方には、どのような役割や活躍を期待しますか。
一番のやりがいは、自分が思い描いた世界を実際に形にできることだと思います。それが誰かに認められて、社会に出ていく瞬間に立ち会えるのは、ものづくりに携わる者としてこの上ない喜びです。私たちが取り組んでいるのは、まだ世の中に存在しない価値を生み出す仕事です。そのため、挑戦する中で未経験の領域や未知の役割に直面することも少なくありません。それがむしろ成長の機会になります。その中で、専門スキルだけでなく、「どうすれば実現できるか」を考え抜く力や、ビジネス視点での判断力も自然と身につきます。
最後に、この記事をご覧の方へメッセージをお願いします。
今の時代は1つの専門を究め続けるだけではなく、複数のスキルを掛け合わせて自分の強みをつくることが求められています。当部門ではそれが自然とできる環境があり、自分のキャリアを柔軟に築いていきたい方には非常に魅力的なフィールドだと思います。 私たちビジョンロボティクス本部は、ニコンという100年企業の中にありながら、スタートアップのような挑戦的な日々を送っています。大企業の安定性と挑戦的な環境の両方を兼ね備えた、非常にユニークな場所です。ものづくりが好きな方や技術を通じて社会に新しい価値を届けたい方、自分のアイデアを本気で形にしてみたい方にとって、ここはまさに挑戦しがいのある場所だと感じています。私たちとともに、まだ見ぬ未来を一緒に創っていきましょう。
※社員の所属やインタビュー内容は取材当時のものです
Pick up