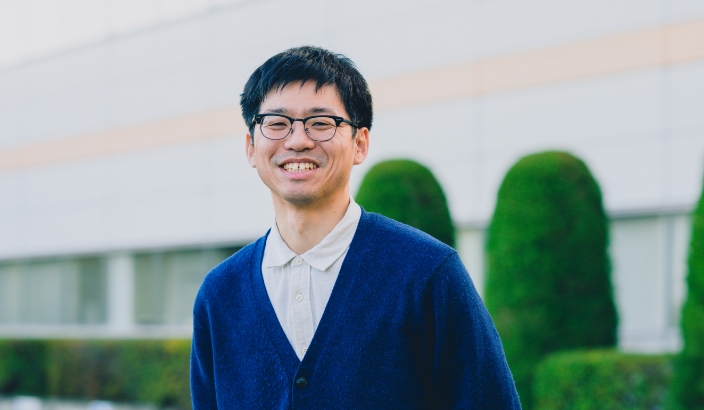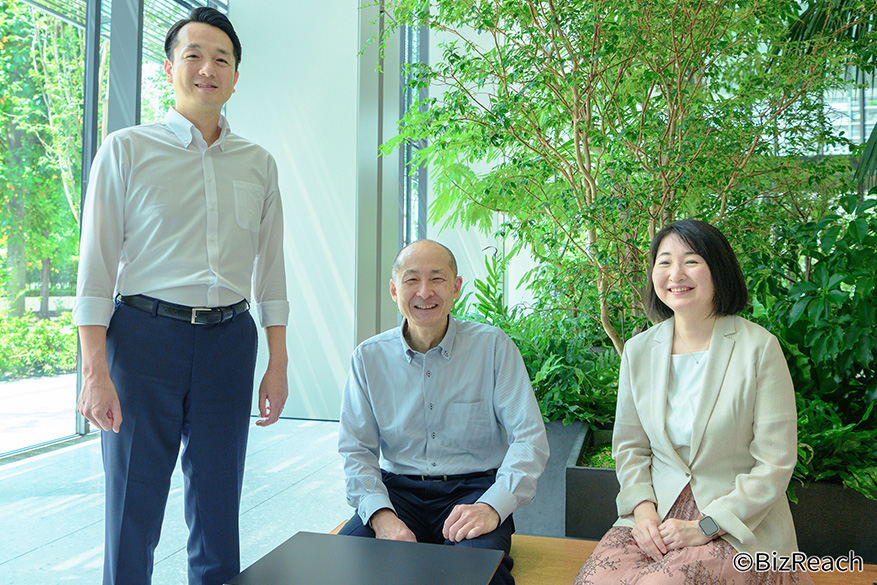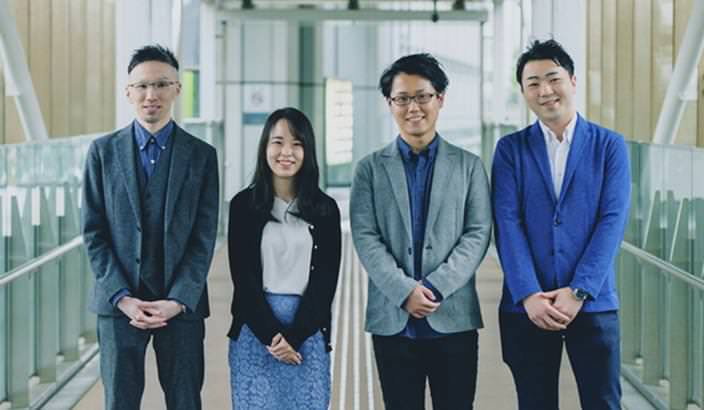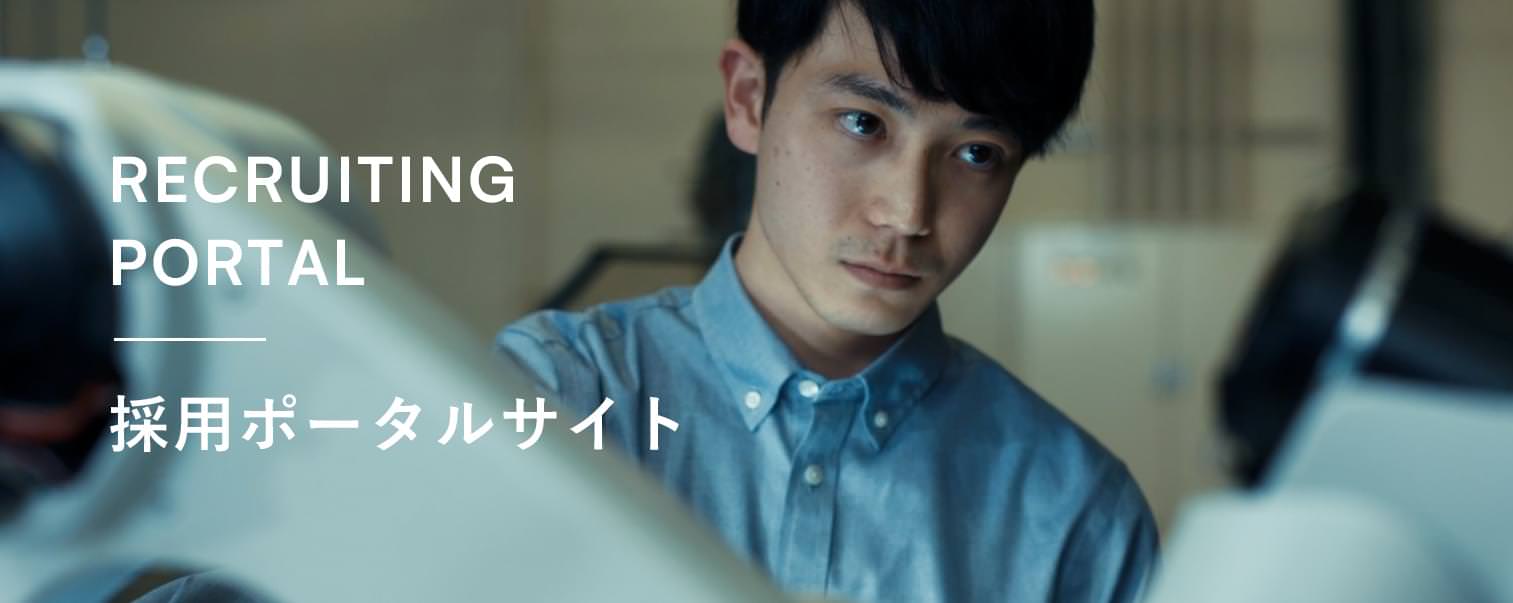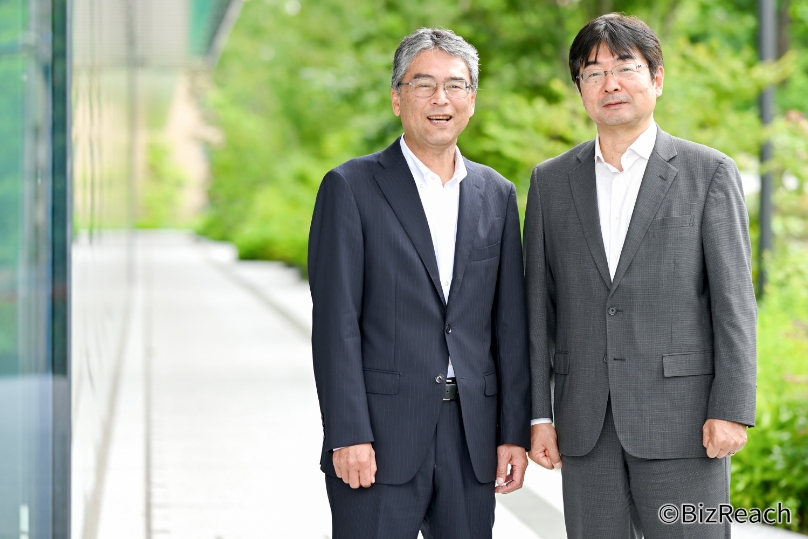
Interview
世界の半導体・FPD市場を支える
「先端露光技術」に迫る
「光利用技術」と「精密技術」を軸に数多くの製品を世に送り出してきた株式会社ニコン。デジタル化が進む時代において、ニコンの最先端露光技術は欠かせない存在となっており、特に半導体・FPD(フラットパネルディスプレイ)分野で市場をリードし続けています。100年以上の歴史で培った技術を活用し未来を切り開く醍醐味について、半導体装置事業部長の森田眞弘氏とFPD装置事業部長の宮崎聖二氏に伺いました。
出典:ビズリーチ掲載記事(2025年7月3日公開)より転載
#01
変革を続けるニコンの
半導体露光装置事業の挑戦と魅力
精機事業本部 半導体装置事業部長(執行役員)/森田 眞弘

半導体露光装置事業の概要と、ニコンならではの強みや独自性についてお聞かせください。
ニコンの半導体露光装置事業の歴史は非常に長く、1980年に国産初のステッパーを世に出したのが始まりです。以来、約45年間で実に60モデル以上もの露光装置を商品化してきました。i線光源露光といったレガシーなものから、ニコンの最先端であるArF液浸露光装置に至るまで、幅広いラインアップを展開しています。 近年では「アライメントステーション」という製品にも力を入れています。二次元構造の半導体が限界に近づき3D構造が主流となるなか、ウェハのゆがみが大きな課題となっており、精度と生産性の両立が難しいケースがあります。ニコンではウェハのゆがみを高精度に、かつ高速に計測する「アライメントステーション」を開発しました。露光装置に組み込む「インライン型アライメントステーション」と、独立にゆがみを計測する「スタンドアロン型アライメントステーション」により高精度な露光を実現しています。
国産初のステッパーを世に出して以来、社会に対してどのような影響をもたらしてきたのでしょうか。
PCやスマートフォン、AIサーバー、自動運転車、電気自動車など、あらゆるデジタルデバイスの基盤を支えているのが半導体です。その性能向上は、線幅の微細化抜きには実現できません。ニコンが線幅を1ミクロンから数10ナノメートルレベルへと劇的に縮小させてきたことで、半導体はより小さく高性能に進化しました。また、この45年間で累計8,000台を超える露光装置を世界中の半導体メーカーに提供してきました。そのなかで、使用済み装置のリフレッシュ再販も進め、資源活用や環境負荷低減といったサステナビリティにも寄与しています。これからも半導体露光装置事業を通じ、より持続可能なデジタル社会の進化に貢献していきたいと考えています。
今後の半導体露光装置事業の展望についてお聞かせください。
今後は急速に変化する市場環境に柔軟に対応しつつ、革新的な製品と新たな事業領域への挑戦を加速していきます。次世代の半導体製造を支える技術開発を積極的に進めていく方針です。 これまでは技術革新によりもたらされる「シリコンサイクル」という景気循環があり、3~4年周期で好況と不況を繰り返してきました。しかし近年では、コロナ禍や地政学リスクなど、予測困難な外部要因の影響が増しています。 こうした状況下でも、ニコンは幅広い製品ポートフォリオを生かし、多様なニーズに柔軟に対応しています。また、主要半導体メーカーとの共同開発を進めることで、最先端のニーズに応える次世代ArF液浸露光装置の開発にも取り組んでいます。製品ラインアップの多様化と、新たな技術・市場への挑戦という2つの戦略を両輪で進めることで、常に一歩先を行く存在として成長を続けていくと確信しています。
これまでのニコンにはない発想で、
新たな風を吹かせてほしい
今回、複数ポジションで採用を強化されている背景と、新たなメンバーに期待することを教えてください。
半導体露光装置事業では製品ポートフォリオのさらなる拡大を目指しており、エンジニア系のポジションで採用を強化しています。特に、お客様の課題を深く理解し、具体的なソリューションとして価値を提供できる「ソリューションエンジニア」の育成・拡充に注力しています。 新たなメンバーに期待することは、何よりも「多様性」です。これまでの発想を打ち破る新鮮な視点や発想は、私たちの事業に新たな風を吹き込み、イノベーションの原動力となると確信しています。 また、ニコンの経営ビジョンである「Unlock the future with the power of light」という精神に共感し、実践していただける方を歓迎します。「light」を自身のキャリアの光と捉え、新しい価値創造に果敢に挑む方にぜひご応募いただきたいです。
半導体装置事業部で働くことの魅力や得られる経験について教えてください。
お客様との距離が近く、自身の技術で直接お客様の成果に貢献できる実感を味わえるのは大きな魅力です。光学、メカ、電気、ソフトウェアの各専門家から構成されるチームで開発を進めることで専門外の知識も自然と習得できる点は、技術者としての視野を広げてくれるでしょう。また、世界中に拠点を持つグローバルな環境でさまざまな国のお客様やメンバーと協働するため、国際的な経験とスキルを磨ける点も魅力です。 風通しの良い職場環境で、キャリア採用者や異業種出身の方も早期に活躍できる土壌があります。充実した技術講座やOJTにより、露光装置の技術を体系的に学ぶ機会が整っており、この分野の経験がない方でも安心して活躍していただけます。積極的に意見を出し、自ら学ぶ意欲のある方にとって半導体装置事業部は、自身のキャリアを大きく飛躍させる環境だと確信しています。

#02
高精細ディスプレイ市場を切り開く、
ニコンの技術と挑戦
精機事業本部 FPD装置事業部長 兼 ガラス事業室担当(執行役員)/宮崎 聖二

はじめにFPD装置事業部の概要と、市場での立ち位置や貴社ならではの強み、独自性をお聞かせください。
FPDとは「フラットパネルディスプレイ」の略で、液晶テレビやスマートフォンの有機ELディスプレイなどが代表例です。FPD装置事業部では、これらの表示デバイスの製造に欠かせないFPD露光装置を提供しています。具体的には、ディスプレイの画素を点灯させるための駆動回路や、タッチ操作などの各種機能を実現する回路を形成する際の露光工程を担う装置です。
FPD露光装置市場におけるニコンの強みは、当社独自の「マルチレンズシステム」です。一般的に装置の大型化にともない、デバイスと同等の広い領域を高い解像度で一括処理する光学系を実現するのは生産性やコスト面で課題が生じやすくなっています。しかし、当社の高性能な小型の投影レンズを複数並べるこの方式を採用することでこれらの課題を克服し、大型基板の高精度・高生産性処理を可能にしています。この独自性が、私たちの競争力の源泉となっています。
今後はどのような差別化戦略や技術開発に取り組んでいくのか、ビジョンをお聞かせください。
まず、私たちはFPD露光装置において極めて重要な2つの核心技術である「光利用技術」と「精密技術」で優位性を築いています。ディスプレイの高精細化・高解像度化が進むなか、投影レンズの光学性能を徹底的に追求しており、この専門集団による高度な光学設計が強みです。 また、3メートル角にも及ぶ巨大なガラス基板を保持するステージを高速で動作させつつ、誤差を0.1ミクロン未満に抑えながら精密に露光する制御技術も、他に類を見ない独自の技術です。複数のパターンを重ねるプロセスにおいて、お客様の生産効率向上に大きく貢献しています。 そして、単なる装置開発にとどまらず、お客様との密接な連携によるソリューション提供にも注力しています。今後は「技術の深化」と「お客様との共創」という2つの柱で競争優位性をさらに強化し、ディスプレイ産業の新たな未来を切り開いていきます。
お客様の課題を引き出し、
新たな製品や技術開発につなげたい
FPD装置事業部で採用を強化する背景と、求める人物像について教えてください。
ディスプレイはスマートフォンやテレビだけでなく、車載モニターやVR/ARデバイスなど用途が広がり、より高解像度・高機能な製品が求められています。さらに近年は、SDGsやCO2削減といった環境課題への対応も重要性が増しています。製造プロセスのエネルギー効率向上や環境負荷低減を実現する新たな開発テーマにも取り組んでいます。こうした多様化・高度化する市場と社会的要請に対応するため、開発・生産・品質保証体制の強化が急務となっており、人材採用を積極的に進めています。 そうしたなかで私たちは、お客様の現場に足を運び、対話を重ねながら課題を深く理解し、それを技術や製品づくりに反映できるエンジニアとともに取り組んでいきたいと考えています。システム・機械・電気・ソフトウェア・光学など、各分野のエキスパートが必要になりますが、共通して重視しているのは、お客様の課題解決に向けて主体的に学び、積極的に提案する姿勢です。ニコンというフィールドを生かし、自身の成長とものづくりの未来に貢献したい方を歓迎します。
FPD装置事業部で働くことで得られる成長の機会や、キャリアパスについてお聞かせください。
FPD装置事業部で働く最大の魅力は、製品の開発から生産、導入、品質保証、そしてお客様へのサポートまで、製品ライフサイクルの全工程に関わる経験ができることです。この一貫したプロセスを通じて、自分が手がけた技術や設計が装置全体でどのように機能し、お客様の現場でどのように役立っているのかを実感しながら成長できます。 また、全工程に携わることで物事を俯瞰して捉える視点が養われ、より実践的な設計能力も身につけられます。コスト意識やお客様に評価される機能開発力など、技術だけでなくものづくり全体を通じた深いスキルと気づきが得られます。 さらに、お客様との直接のコミュニケーションを通じて、現場のリアルな課題に向き合う場面も多く、論理的思考力や問題解決力、さらにはコミュニケーション能力の向上も期待できます。こうした多面的な経験を積むことで、技術者としての専門性とともに、広い視野を持ったプロフェッショナルへと成長できる環境です。

※社員の所属やインタビュー内容は取材当時のものです
Pick up